新生児期も過ぎ、3~4ヶ月はある程度寝てくれるようになったのに、5ヶ月過ぎてから夜泣きが始まってどうしたものかと、悩まられている方がいらっしゃると思います。
夜泣きの絶対的な解決方はありません。だけど、、、
残念ながら、こうしたら夜泣きはピタリと収まる!という夢のような方法はありません。
ただ、親心としては泣いて困っている我が子にどう関わっていいか、悩みます。
親としてできることはどんな事を気をつけたらいいのでしょうか?
赤ちゃんの眠りのサイクルを知る
赤ちゃんの眠りのサイクルは大人と比べると短いのです。
レム(浅い眠り)とノンレム(深い眠り)を1サイクルとします。
大人は睡眠時間7~8時間の間に1サイクル=90分を繰り返す。
生後3ヶ月~1歳は睡眠時間14~15時間のうち1サイクル50~60分を繰り返す。
赤ちゃんがすぐに起きてしまうのは、このサイクルの時間が短いためなのです。
赤ちゃんは眠りの練習中
もともと人間は25時間の体内時計を持ち合わせています。
地球時間の24時間に合わせる練習を赤ちゃんは練習していくのです。
新生児期は昼も夜も関係なく、睡眠と授乳の繰り返しです。
2ヶ月~4ヶ月でこの地球時間に合わせる練習が開始されるのです。
生後5ヶ月からは体内時計がうまく働くようになってきます。
5ヶ月、1歳、2歳から夜泣きが始まることも
うまく働き始めるようになった体内時計も環境の変化で、夜泣きはしてしまうものです。
まずは赤ちゃんのうちは、朝の光を受け、夜は暗くしましょう。
朝はお部屋を明るくし、陽の光を目から感じさせましょう。
夜は大人の都合と折り合いながら、睡眠の環境設定を設けてあげましょう。
暗くなったら、カーテンを閉め電気を消しましょう。
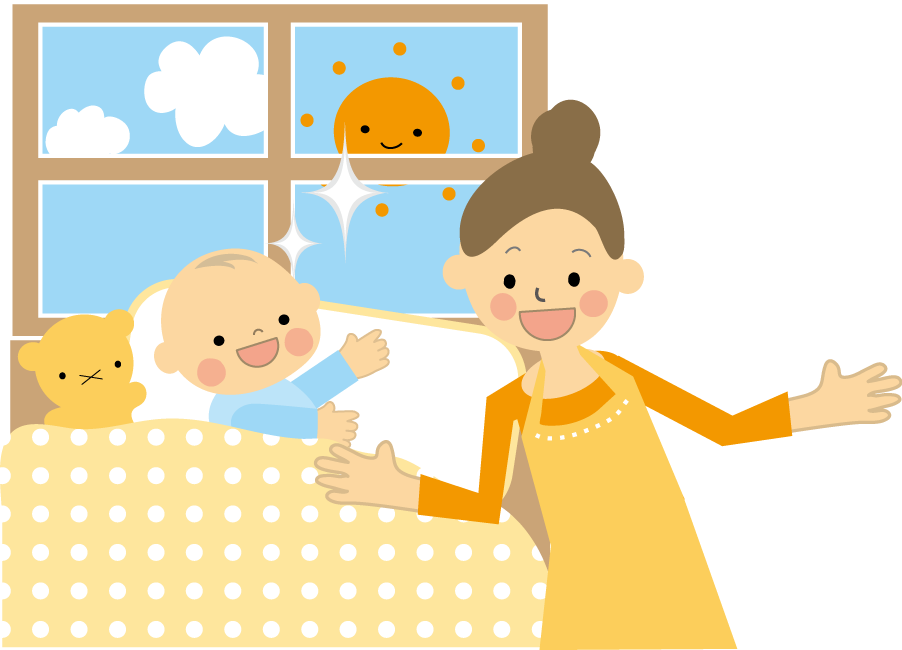
メラトニンを分泌させるために
メラトニンという眠りを誘うホルモンは、室内を暗くすることがポイントです。
明かりを消すことで、脳への刺激をなくします。
お母さんも休息を
夜泣きで辛いのは、お母さんも辛いと思います。
育児の他、家事もこなさないとはいけませんが、ほどほどにでも大丈夫。
大人が体調不良だと、育児がさらに大変です。人に頼るのは罪ではありません。
おじちゃんおばあちゃん、一時預かり、ファミリーサポートなどなど。
ちょっと勇気を出して、休んでみましょう。
育児はみんなで、手を取り合い支え合いましょう。
